

○ 山地から下流、湖までと広く生息し、少し汚れた水質でも耐えられる。
生きてるときは腹部がきれいな緑色をしており、白くフサフサしたエラがある。
○ 繁殖時期は4月〜10月。
○ 笹ヶ瀬川では普通に採集できる。


○ コガタシマトビケラ属に比べていかつい。色もやや濃い。
○ 繁殖時期は4月〜10月。
○ 笹ヶ瀬川では普通に採集できる。


○ 幼虫は河川下流域に生息する。
○ 成虫は晩春から夏にかけて出現する。
○ 笹ヶ瀬川では主に囲池で採取できる。
○ 特徴は頭が凹んでいるところである。


○ 幼虫は河川上流域から下流域の早瀬や平瀬の礫底に生息する。
石と石の間に網を張り、網にかかった小さな動植物破片や藻類などをえさにしている。
○ 1年1化あるいは2化でどちらになるのかは種や生息している河川の水温で決まる。
年2世代の場合には、越冬世代の成虫は夏に、非越冬世代の成虫は秋に見られる。
○ 笹ヶ瀬川では栢谷で少しだけ見たが、主に旭川で採集できる。
○ この顔は他にない。この顔見たら絶対にヒゲナガカワトビケラ決定!!しかもデカイ。


○ 幼虫は河川上流域から下流域の流れが穏やかな場所に生息する。
巣には3〜4対の大きな翼石をつける。
○ 成虫は春から秋にかけて出現する。
○ 笹ヶ瀬川ではあまり採集できない。
○ 石に入ってるのを見たらだいたいこいつ。




○ 笹ヶ瀬川では栢谷で採集できる。
○ エラをもたない場合がほとんど。これで初心者でもシマトビケラと見分けがつくぞ。
○ 背中の模様も特徴的。なんとなくブヨブヨしてる。
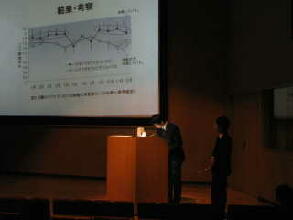

○ 背中の模様がナガレトビケラ属と似ているが、太さとお尻がぜんぜん違う。
○ きれいな水の指標生物なので、大切に扱いましょう。


○ ちゃんと同定してないから正確には違うかも(^_^;)
○ 特徴である巣が発見できなかったので微妙。ただ手の長さや体の形でたぶんそう。
詳しく知りたいなら上唇背面の横一列に並ぶ長い毛の数を見てみよう♪
○ 旭川でのみ採集。

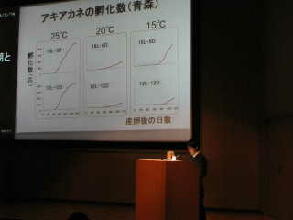
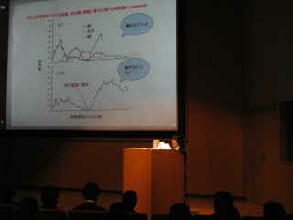

○ 旭川で採集できる。
○ 中胸の背面に黒くて細いキチン板がある。○のところ。
○ 前の方の腹節は頭部や胸部に比べて大きい。
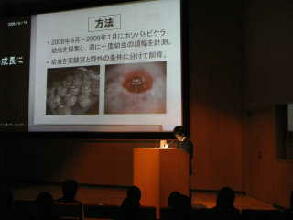



○ シマトビケラ科に似ているが、エラがないことで別種だと判別できる。
○ 死んでいるときにシマトビケラ科は丸くなることが多いが、こいつは伸びたまま死ぬ。
○ お尻のかぎ爪の形も特徴。


○ 旭川でのみ採集。
○ 何かはわからない。余力があったら同定して。もしかしたら新種かも(笑)